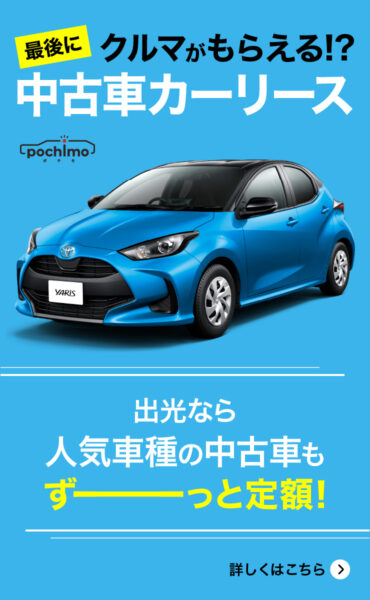車にしめ縄をつける理由とは?時期やつける方法、処分の仕方を解説

しめ縄は家の玄関や入り口につける正月飾りの一つです。
一般的には家につけるものとされますが、車につける人もいます。
しかし、最近はしめ縄飾りをつけた車は減ってきており、見たことがないという人も少なくありません。
そこで、今回は車にしめ縄をつける理由やつけなくなった理由、つけ方、使い終わった後の処分方法などについて詳しく解説します。
飾りの意味合いやしめ縄をつける時期も紹介するので、ぜひ参考にしてください。
ポチモは毎月定額でクルマに乗れる、出光興産の新車・中古車のカーリースです。
頭金・ボーナス払い0円、走行距離の制限がなく、最後に必ずクルマがもらえます!
ずっと定額でお気に入りのクルマに乗れる「ポチモ」が気になる方は、以下のバナーからご確認ください。

INDEX
車にしめ縄をつける時期はいつからいつまで?

車にしめ縄(しめ飾りとも)をつける時期は、一般的な正月飾りと同様12月13日から12月28日までの間です(目安)。
車に限らずしめ縄をつけるのは、ほかの正月飾りと同じタイミングでつけるのがよいとされます。
13日は正月始めにあたり、神社などでは正月に向けた準備を始めます。
また、しめ縄をつけるのが28日までとする理由は、29日は「二重苦」を連想させる日にちであり、31日は一夜飾りとなってしまい避けた方が良いとされているためです。
地域によっては29を「ふく」と呼び、縁起がよい日にちとするケースもありますが、一般的には28日までで遅くとも30日には飾ってしまいます。
しめ縄を外す時期
しめ縄を外す日は1月7日が一般的です。
関西では15日に外す傾向にあり、早ければ7日頃、遅くとも15日頃には外すようにしましょう。
関連記事:ガソリン車はいつまで乗れる?日本の取り組みや他車のメリット・デメリットを紹介
車のしめ縄を車内・車外につける方法と注意点

車にしめ縄をつける方法は、車外と車内の2パターンがあります。
しめ縄をつける際の注意点もあるため、自分の車にしめ縄をつけたい人は併せて確認しておきましょう。
関連記事:車をぶつける夢の意味は?事故の夢を見るときの心理や宝くじ当選の前触れという噂について紹介
車外につける方法と注意点
車外につける場合、前面のフロントグリルやバンパーが一般的で、メーカーロゴの下あたりがおすすめです。
走行中に落ちないようしっかりとつけるのがポイントですが、強度を求めワイヤーなどで固定すると車を痛める原因となります。
車に傷がつくものは使用せず、紐や結束バンドでくくりつけるようにしましょう。
注意点として、しめ縄をつけた後はナンバープレートやランプが隠れていないか確認することがあげられます。
ナンバープレートが隠れていると、取締の対象となる可能性があります。
関連記事:358のナンバープレートはなぜ人気?意味や避けるべき数字について解説
車内につける方法と注意点
車内に適したしめ縄は、ミラーにつけるタイプやダッシュボードに置くタイプなどがあります。
ミラーの下につけるタイプは正月飾りのしめ縄というより、通年通して売られている装飾アイテムが多いです。
そのため、正月飾りとして特別に飾りたい場合は、ダッシュボードに置くタイプを選ぶとよいでしょう。
注意点として、走行中の安全に支障がでないように飾ることがあげられます。
例えばミラーにぶら下がっているタイプであれば、走行中の視界が妨げられる可能性があるでしょう。
ダッシュボードに置くタイプの場合、走行中に外れて足元に落下するかもしれません。
運転中の危険やトラブルにつながらないよう、飾った後は運転に支障がないか確認するようにしましょう。
関連記事:日産のe-powerとは?電気自動車やハイブリッド車となにが違うのか徹底解説
車にしめ縄をつけなくなった理由

正月文化の希薄化や車を取り巻く環境の変化により、車にしめ縄をつける人が減りました。
ここでは、車にしめ縄をつける人が減った理由をいくつか紹介します。
現代車はしめ縄をつけにくくボディを傷つけやすい
車にしめ縄をつけなくなった理由は、車にくくりつけにくく、つけようとするとボディを傷つけてしまう可能性が高いためです。
古い車の場合、デザインや冷却の観点から角ばっていることが多く、フロントグリルにしめ縄をくくりつけやすい形状でした。
しかし、現代は安全への配慮や空気抵抗の観点からフロントグリルが小さく、曲面となっている車が多いです。
車のフロント部分は風を受け流す役割も担っていることから、しめ縄が風にあおられ車を傷つけるリスクも高まっています。
関連記事:高齢者マークは何歳から?車のどこに貼ればよいの?ルールや効力について紹介
正月文化の希薄化でしめ縄をつける人が減っている
近年、しめ縄に限らず正月文化が希薄になりつつあります。
車にしめ縄をつける人の総数が減り、文化として廃れ始めていることが理由に挙げられるでしょう。
また、車は一家に一台という概念も薄まり、現在は車を所有しない人も少なくありません。
車が必要なときだけレンタカーを借りたり、シェアしたりと生活習慣の変化も合わさって、しめ縄をつけた車を見る機会が減っているようです。
関連記事:中古車を減価償却で経費計上するには6年落ち?4年落ち?
そもそもしめ縄とは?

最近は見る機会が減りましたが、正月飾りとして車にしめ縄をつけることがあります。
家の飾りとして見ることの方が多いかもしれませんね。
ここでは、車にしめ縄をつける理由や飾りの意味合いを見ていきましょう。
しめ縄をつける理由は伝統が関係している
正月飾りとして知られる「しめ縄」ですが、実は正月だけの飾りではありません。
そもそもしめ縄は神様が降り立つ場所の目印や降り立った神聖な場所を示すための道具で、魔除けの意味もあります。
そのため、神社では通年しめ縄が飾られており、神社内で祀られている大きな岩や木、鳥居などで見る機会が多いです。
しめ縄を正月に飾る理由は、正月が豊作や健康、安全に携わる「年神様(新年の神様)」を迎える日本の伝統行事であることが挙げられます。
言い換えるなら、年神様を迎えるための目印としてしめ縄を飾り始め、それが伝統となり、安全運転を祈って車にもつけるようになったのです。
関連記事:生年月日占いの四柱推命(しちゅうすいめい)で相性がわかる?簡単に解説!
飾りの意味合いは?

正月飾りのしめ縄と通常のしめ縄では飾りが異なります。
正月飾りのしめ縄は、めでたい神様である年神様を迎えるためです。
通常のしめ縄の飾りと異なる理由は諸説ありますが、昔の人が通常のしめ縄にめでたいとされる縁起物をつけ、年神様に縁起物にちなんだ祈願をするアレンジを行った結果、それが伝統となり現在の形になったといわれています。
地域によってしめ縄につく飾りは異なりますが、一般的には橙(だいだい)や裏白(うらじろ)などを加えるのが定番です。
橙は実が落ちにくいという性質を持っており、「一族の代々繁栄」を祈り飾られます。
裏白は葉の裏が白く、2枚の葉が左右に向き合い大きく広がる様を「清廉潔白で夫婦円満」に見立てて飾られています。
正月飾り・しめ縄の処分方法やタイミング
12月13日に正月始めとして準備が始まった一連の正月行事は、1月15日前後に行われるどんど焼きを区切りに終了するといわれます。
ここでは、正月飾り・しめ縄の処分方法や時期について、詳しく解説していきます。
しめ縄処分の適切な時期
多くの場合、しめ縄の処分は小正月(1月15日)までに行うのが一般的です。
これはあくまでも一般的なタイミングであり、正月飾りやしめ縄の処分時期は地域や家庭によって異なります。
例えば、1月7日に飾りを下ろす地域もあります。
地域の習慣に従うことが大切であると覚えておきましょう。
しめ縄の処分方法
どんど焼きという正月の縁起物を焼却処分する行事で、神社やお寺、小学校などで処分するのが一般的です。
飾り終わったしめ縄は、どんど焼きを行う場所へ持ち込んで焼却処分をしましょう。
どんど焼きを行っていない地域では、神社で正月飾りの処分を受け付けていることがあります。
その場合、神社に持ち込み処分のお願いをするとよいでしょう。
神社やどんど焼きに持ち込めない場合、通常の燃えるゴミとして処分することになります。
縁起物であるため、自宅で燃えるゴミとして処分する場合は塩で清めてから処分するようにしましょう。
以下にどんど焼きを含めた一般的な処分方法を紹介します。
1. 神社での焚き上げ式(どんど焼き)
どんど焼きは、正月飾りやしめ縄を神社で焚き上げる行事です。
神様への感謝の意を込めて、一年の無病息災を祈る意味があります。地域によっては、1月14日や15日に行われることが多いです。
2. 自宅での処分
自宅で処分する場合は、自治体の指示に従い、燃えるごみとして出すことが一般的です。
ただし、地域によっては特別なルールが設けられている場合もありますので、事前に確認が必要です。
3. リサイクル
最近では、正月飾りやしめ縄をリサイクルする動きも見られます。
例えば、しめ縄を解いて畑のマルチング材料として利用するなど、環境に優しい方法も選択肢の一つです。
関連記事:燃料電池車が普及しない理由とは?今後の見通しについても解説
まとめ
正月は健康や安全を祈り、年神様を迎え入れる日本の伝統行事です。
年神様を迎え入れる場所を示す道具がしめ縄ですが、最近は正月文化の希薄化により、しめ縄をつける車が減ってきています。
なお、車にしめ縄をつける場合、走行に問題がないか、ナンバープレートは見えているかを確認することが大切です。
安全な走行が可能か確認した上で、一年間の健康や安全に感謝をしつつ、しめ縄をつけた車でドライブを楽しんでみてはいかがでしょうか。
ポチモは毎月定額でクルマに乗れる、出光興産の新車・中古車のカーリースです。
頭金・ボーナス払い0円、走行距離の制限がなく、最後に必ずクルマがもらえます!
ずっと定額でお気に入りのクルマに乗れる「ポチモ」が気になる方は、以下のバナーからご確認ください。