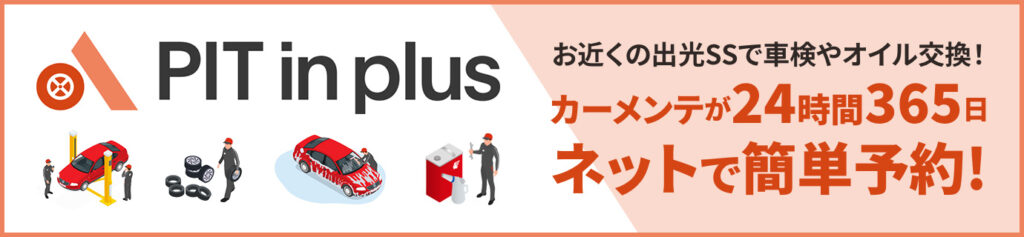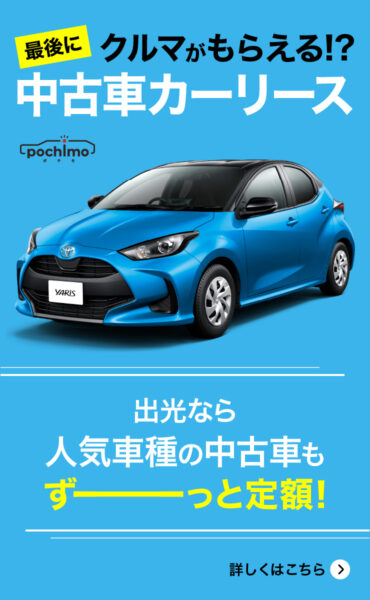バニングカーはなぜ消えた?現在どうなったのか歴史とともに解説

バニングカーとは、バンタイプの車両を大胆にカスタマイズしたカスタムカーの一種で、特に1980年代から1990年代にかけて日本で大きなブームとなりました。
バニングカーの特徴は、車全体を覆う派手なエアロパーツや巨大なリアウイング、ハデなグラフィック塗装、そして内装の豪華な改造です。
この記事では、バニングカーが消えた理由を探り、歴史やベースとなる車、ハイエースについても併せて説明するため、車の改造を検討している人は参考にしてみてください。
関連記事:【2024年】ミニバンおすすめランキング!人気車種20選!選び方も解説
INDEX
バニングカーとは
ワゴン車をベースにしたカスタム手法を和製英語で「バニング」といい、その改造車両を「バニングカー」といいます。
一般的に、バニングカーにはエアロパーツが取り付けられいます。エアロパーツとは、車のボディの外側に取り付けられる部品のことで、ドレスアップ以外にも高速走行時の安定性向上や軽量化を目的として付けられます。
バニングカーはエアロパーツを後ろに大きく跳ね上げた形で装着して、車の外観を個性的で派手なものに変えているのが特徴です。
また、フロントガラスと前部座席のドア以外の窓を覆って、フラットな見た目にしている場合もあります。
そのほかにも、装飾ランプや巨大スピーカーを付け加えるなどして、車を自由にカスタマイズしています。
車体は、ビビットなカラーやパステル調の塗装で塗られたり、持ち主が好きなアートやアニメなどのイラストが描かれたりもしている車もあります。
遠くからでも目を引き、街中でも存在感のあるデザインです。また外装だけでなく、内装も改造しているバニングカーもあります。
豪華な皮のシートが使われていたり、スロットマシンが設置されていたりなど、改造の仕方は人によってさまざまです。
バニングカーは、最近はあまり見かけなくなってきている車です。
バニングカーが消えた理由
かつて大きな盛り上がりを見せたバニングカー文化が衰退した背景には、いくつかの要因が複雑に絡み合っています。
その理由を以下に考察していきます。
社会の価値観やライフスタイルの変化
1980年代から1990年代は「ハデさ」を強調することが重要視された時代でした。派手な見た目や「目立つこと」がステータスとされる風潮があり、バニングカーはその象徴的な存在でした。
しかし、2000年代以降、ミニバンの実用性や燃費の良いコンパクトカー、SUVの人気が急上昇。車はより「生活を豊かにする道具」としての実用性が重視されるようになりました。
これにより、派手さやカスタムへの関心が薄れ、時に「ダサい」とまで言われるようになっており、バニングカーの需要は減少していきました。
法規制・車検・排ガス規制の影響
バニングカーの多くは、外装のエアロパーツや巨大なウイングが特徴的ですが、時に道路運送車両法や保安基準に抵触することもありました。また、車検で問題となりやすく、維持するためのハードルが高かったのです。
バニングカーの派手な改造には多額の費用が必要で、加えて維持にも手間がかかります。これに対し、実用性があり手軽に楽しめる車両カスタムが主流となり、バニングカーのように「派手さ優先」のカスタムは敬遠されるようになりました。
さらに、2000年代以降は排ガス規制が強化され、特に古いバンやキャブオーバー車両が使用しにくくなりました。
多くのバニングカーはこうした規制をクリアできず、徐々に姿を消していきました。
バニングカーの歴史
バニングカーの発祥地はアメリカの西海岸です。
1960年代のアメリカ・カリフォルニア州にて、ピックアップトラックがカスタムされるようになったことが始まりとされています。
ピックアップトラックとは、前方にボンネットと乗員スペース、後方に開放式荷台を備えた車両のことを指します。これは、キャンピングカーのように使うために改造されていました。

自分の手で自由に改造・改良を行うバニングカーは、次第に若者の間でも流行りはじめていき、そのうちにカルチャーとして定着するようになりました。
さらに、華美な装飾やインテリアが用いられ、より個性豊かなカスタム車が登場します。
特に、まるで家の中にいるような内装スタイルが好まれました。
1980年には「バン・バニング・バン」という映画が公開され、世界中でバニングカーの存在が知られていきます。1980年代ごろからは、日本に豪華なアメリカ車が輸入され、バニングカーの文化を踏襲して日本でも車の改造を楽しむ人が増えました。
バニングカーのベースとなっていた車として、ダッジが製造・販売していたキャラバンやトレーズマン、シボレーが製造・販売していたアストロなどの輸入車が挙げられます。
また、アメリカの車だけでなく、トヨタが製造・販売するハイエースや日産が製造・販売するキャラバンといった国産車も使われました。
日本のバニングカーの特徴は、本場より派手なデザインであることです。
バブル期にはバニングカーブームが到来し、大型のエアロパーツを取り付けたり、爆音のオーディオを搭載したりする車もあったようです。
しかし、次第にバニングカーの台数は減ってきました。
理由としては、日本の車に関する法令にあります。日本の規制はアメリカよりも厳しくなっています。
違反となる改造行為を行う車は厳しく取り締まりが行われ、バニングカーも徐々に数が少なくなっていきました。
多くのバニングカーが取得していた8ナンバーも、安易に取得できないように法令が改正されています。
規制で数が減ったとはいえ、一部の愛好家の間では、バニングカーは長く愛される文化でもあります。

バニングカーのベースとなる車
バニングカーのベースとして利用される車には、アメリカ車のキャラバンやアストロなどがありました。
また、ハイエースなどの国産車も、輸入車に比べて安価に購入しやすいという理由からバニングカーのベースとして選ばれています。
ハイエースは、広い車内空間を持っていることが大きな特徴です。
長距離走行にも耐えられる頑丈なつくりで、荷物も多く載せられます。
そのため、宅配や旅客輸送など商用にも利用されています。
ハイエースの荷室は、より多くのものが載せられるようにシンプルな設計です。
レイアウトを自分好みに変更したり、DIYでパーツを付け加えたりすることに向いています。
ハイエースは、改造の自由度の高さから、バニングカーのカスタムに適しているといえるでしょう。
また、ハイエースには、100系と200系があり、バニングカーのベース車として多く見かけるのは100系ハイエースといわれています。

関連記事:ハイエースの内装を便利にカスタムするパーツを紹介!
ハイエースの種類
ハイエースには、「バン」「ワゴン」の2種類があります。
バンは商用車ですが、カスタムの自由度が高く、バニングカーのベース車として向いているといえるでしょう。
ワゴンは、居住性を重視する場合におすすめします。
乗用車として製造・販売されているため、乗車人数が増えても車内空間にゆとりがあり、座りやすいのが特徴です。
ハイエースの魅力
ハイエースには、バニングカーのベースとして利用される以外にも、さまざまな魅力があります。以下でそれぞれ詳しく解説します。
車中泊ができる
ハイエースは、広い車内空間が魅力であり、キャンピングカーとしても利用されることが多い車です。
座席シートを倒してフラットにし、車内で寝泊まりできる広さを確保できます。
また、ハイエースにはキッチンを搭載可能です。
さらに、普通免許で運転できることも大きなメリットです。
マイクロバスやトラックをベースにしてキャンピングカーとして利用しようとすると、大型免許など別の運転免許を取得する必要があります。

多くの荷物が積める
ハイエース バンは、性能のよいエンジンを搭載しており、重量のある荷物を運べるスペックを持っています。
ガソリンエンジンとディーゼルエンジンのどちらかが選択でき、特にディーゼルエンジンはガソリンエンジンと比べてトルクが高いのが特徴です。
また、ハイエース バンの堅牢なボディ構造や頑丈なサスペンションは、重い荷物による負荷にも耐えることができます。
ハイエース ワゴンは「GL」「DX」「グランドキャビン」の3つのタイプがあり、どのタイプも十分な荷室スペースを確保しています。
GLには、サイドに格納してスペースアップができる「最後列スペースアップシート」を標準装備されているのが特徴です。
安全性能が優れている
ハイエースは、事故を起こさないための安全性能が高く、安心して運転できる車です。
たとえば、前方の車両や歩行者を検知して警報ブザーとディスプレイ表示で衝突の可能性を運転手に知らせます。
ブレーキサポート機能もあるため、衝突回避・被害軽減に役立ちます。
ほかにも、メーカーオプションで車の後方カメラの映像をインナーミラー内のディスプレイに表示することも可能です。
さらに、ボディ構造は、万が一対人事故を起こした場合に衝撃を緩和する設計となっています。
まとめ
この記事では、バニングカーとは何かを説明しました。
バニングカーとは、バン車をベースにした改造車のことです。1960年代ごろにアメリカで生まれ、日本には1980年代にやってきました。
車のボディにエアロパーツを付けて、大きく派手に見せるデザインが特徴的です。
ベースとなる車には、荷室が広く改造しやすいトヨタのハイエースが選ばれることが多いとされています。
ハイエースは、バニングカーとして利用されているほか、広い荷室とレイアウトのしやすさからキャンピングカーとしても人気があります。
画像出典:トヨタ自動車株式会社