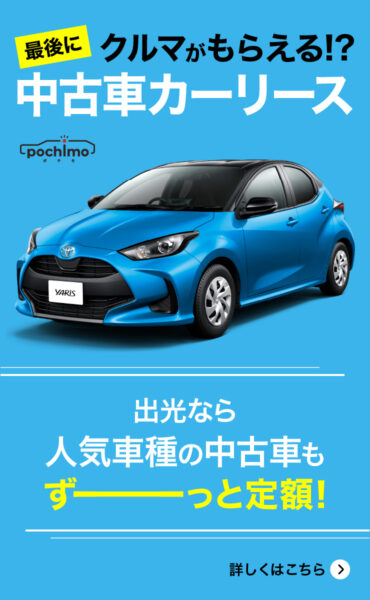モビリティとは?自動車とどう違う?意味やサービスを解説!

近年、自動車産業で「自動車」という言葉と混じって「モビリティ」という単語を耳にするようになりました。
カタカナやアルファベットの略語などの横文字が増えてきているので、「モビリティ」も単なるその一環かと思っている方もいらっしゃるでしょう。「モビリティ=乗り物や移動」というイメージがあると自動車などが頭に思い浮かぶかもしれませんね。
ここでは、「モビリティ」の意味や関連したサービスをご紹介します。
自動車産業の発展とも言える「モビリティ」について興味を持っていただければ幸いです。
関連記事:モビリティ社会への課題とは?事例や現状をわかりやすく解説

INDEX
モビリティ(Mobility)とは
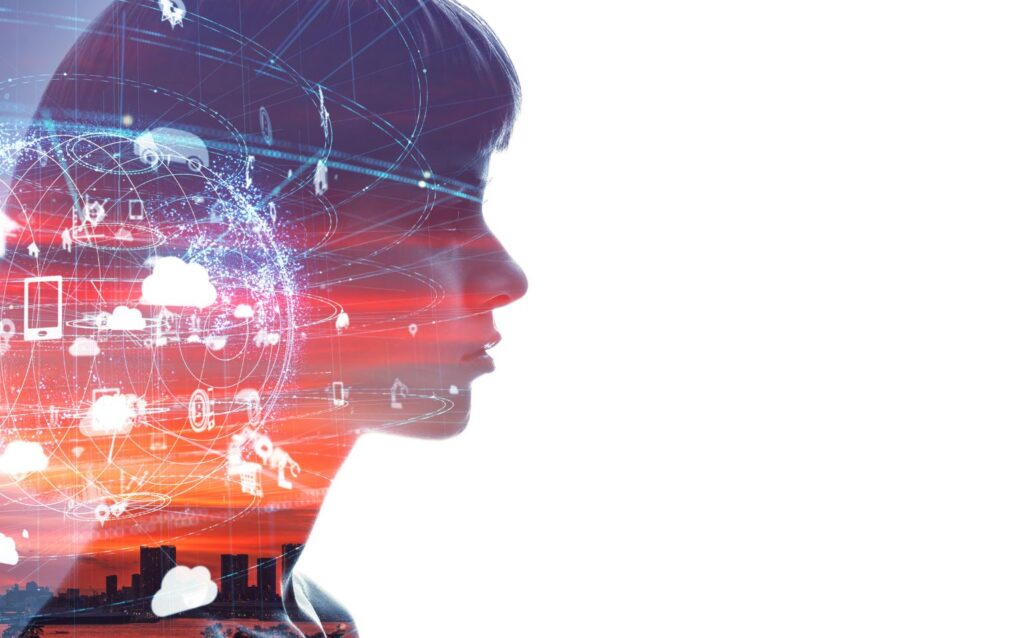
モビリティ(Mobility)という英語を直訳すると、「可動性」や「移動性」「流動性」などを意味します。
身近な例だと「モバイル(Mobile)」の関連語と考えると理解しやすいかもしれません。
つまりモビリティとは、一般的には人やモノが移動する能力や手段を指すのですが、近年では、都市環境における交通手段や交通システムの変革を指して「モビリティ」という用語が使われることが増えています。
モビリティの例
モビリティの例は以下の通りです。
- 自家用車
- バス
- タクシー
- トラック
- オートバイ
- 自転車
- 原動機付自転車
- 電車
- 電動キックボード
- ドローン
- 空飛ぶクルマ
上記の通り、モビリティには移動や輸送に関わるあらゆる手段・手法が含まれます。近年では、電動キックボードやドローン、空飛ぶクルマなど、モビリティの多様化が進んでいます。
モビリティの目指す所
モビリティの目標は、交通の効率性、持続可能性、アクセシビリティ、包摂性、利便性、安全性を向上させることです。
例を挙げると、交通渋滞の軽減、排出ガスの削減、公共交通機関の利便性向上などの社会的なことから、交通事故の減少など個人にまつわるものまで含まれます。
また、人々が必要な場所に効率的に移動できることによって、生活の質が向上し、都市の持続可能な発展が促進されると考えられています。
地球環境と調和した持続可能な移動手段を提供し、人々の日常生活をより便利にし、安全で公平な移動を実現するために取り組んでいます。
モビリティの背景
近年モビリティと言われ出した背景には、技術の進歩やデジタル化の影響が大きくなっていることが挙げられます。
AI(人工知能)やビッグデータの活用、IoT(インターネット・オブ・シングス)の導入、スマホアプリのようなモバイルアプリケーションの普及などが、モビリティの変革を支える要素となっています。
総じて考えると、モビリティは、移動手段や交通システムの革新を指し、人々がより便利かつ持続可能な方法で移動できるようにするための取り組みや概念を包括する言葉と言えます。
関連記事:シーン別!ドライブの時に役立つおすすめアプリを紹介!
モビリティー事業(Mobility business)

モビリティー事業(Mobility business)は、人や物の交通や移動に関連する産業やさまざまなサービスや事業を指します。
具体的には、輸送手段や移動方法に関わるサービスや技術の提供のことです。自動車メーカーや公共交通機関、シェアリングサービス、交通インフラ、モビリティテクノロジーなどが含まれます。
都市化や技術の進歩により急速に変化し、持続可能性や利便性の向上に向けた取り組みが行われています。
では、現在モビリティ事業でどのような動きがあるのでしょうか。
以下のようなものが、典型的なモビリティー事業の例と言えるでしょう。
自動車メーカーによるモビリティーサービス
一部の自動車メーカーは、従来の自動車販売に加えて、車両の所有から利用へのシフトを促進する自社の車両をシェアリングサービスやレンタカーサービス、カーリースなどとして提供するなど、新たなビジネスモデルを展開しています。これらは柔軟な移動オプションを提供し、都市部の交通問題や環境負荷を軽減します。
関連記事:カーシェアリングとは?仕組みや特徴をレンタカーやカーリースと比較
ライドシェアサービス
ライドシェアサービスは、個人が自家用車を運転し、アプリを通じて顧客と共有するサービスです。利用者はアプリを介して車を予約し、料金を支払います。主なプレーヤーにはUberやLyftがあり、利用者は便利で手頃な価格の移動手段を享受できます。
これにより、個人間での移動がより便利になりました。
電動車や自動運転技術
モビリティ事業は、電気自動車(EV)や自動運転技術の開発・導入によって大きな変革を遂げています。
電動車は環境にやさしく、エネルギー効率が高いため、持続可能な移動手段として注目されています。また、自動運転技術は安全性や効率性を向上させ、交通事故や交通渋滞の軽減に貢献します。
モビリティ事業者は、これらの技術を取り入れることで、より革新的で競争力のあるサービスを提供し、顧客ニーズに応えることが期待されています。
関連記事:自動運転が可能な車種を一覧で紹介!レベル別の違いも解説
これからのモビリティ
もうすでに実現に向けて動いている分野を一部ご紹介します。
自動運転
2023年4月1日に自動運転レベル4の運航許可制度を含めた改正道路交通法が施行されます。
日本の自動車メーカーであるホンダは2025年をめどに自動運転レベル4を普及させる方針です。
また、自動車メーカーのトヨタは2018年に自動運転レベル4である自動運転シャトル「e-Palette」を発表し、2021年に開催された東京オリンピックの選手村で導入されました。
しかし、選手との接触事故を起こしてしまい、安全性への懸念が高まりました。
トヨタは今後「e-Palette」の安全性の向上に向けて、自動運転技術を高めていくと考えられます。
関連記事:自動運転技術が一番進んでいるメーカーはどこ?国内メーカーや海外メーカーの状況を紹介
関連記事:自動運転レベル5が作る世界と現状を解説!完全自動運転は実現できるのか
ZEV(ゼロエミッションビークル)
ゼロエミッションビークル(Zero Emission Vehicle、ZEV)は、環境に悪い排出物を生み出さない車両のことを指します。
自動車の動力源は、ガソリンエンジン車から主に電気自動車への移行が進んでいます。
電気自動車としては、日産 サクラや三菱 eKクロスなどが2022年に注目を浴びました。
電気だけでなく、水素自動車のトヨタ MIRAIやクリーンディーゼルのマツダ MAZDA2など各メーカーがゼロエミッションに取り組んでいます。
関連記事:ZEV補助金対象車一覧と補助金額
eVTOL(空飛ぶクルマ)
移動時間の短縮や渋滞の緩和などの日常的な理由や、災害時の救出時への使用のために開発が進んでいます。
ボディタイプとしては、複数のプロペラを装備したドローンタイプか、飛行機のような翼のあるタイプの2種類に分類されます。
航空機やヘリコプターとの大きな違いは、燃料が不要であり電力で駆動できることです。
パーツの数を大幅に減らせるので整備コストを下げることが可能です。
開発に向けて自動車メーカーも多数参入しており、トヨタ、ホンダ、スズキ、アウディなどが表明しています。
関連記事:エアモビリティとは何なのか?国内外の開発状況について紹介
MaaS(Mobility as a Service)
MaaS(Mobility as a Service)とは、個別の交通手段やサービスを単独で利用するのではなく、複数の交通手段を統合し、1つの総合的な移動サービスとして提供するアプローチのことです。
MaaSは、デジタル技術やモバイルアプリケーションを活用して、利用者一人一人の移動ニーズに合わせた交通手段を容易に検索、予約、支払いまでを簡潔にできるようにします。
具体的には、公共交通機関(バス、電車、地下鉄)、自転車シェアリング、カーシェアリング、タクシーなど、さまざまな移動手段を1つのプラットフォーム上で統合し、利用者一人一人に利便性と柔軟性のある移動手段の提供を一括で行うことができるのです。
関連記事:MaaS(モビリティ・アズ・ア・サービス)とは?簡単に解説
モビリティの課題
モビリティー事業の導入には、規制やインフラの整備、プライバシーとセキュリティの保護、交通ルールや安全基準の確立などの課題も存在します。
また、モビリティー事業は地域や国によって異なる法律や規制にも影響を受けるため、地域の特定の要件や制約に対応する必要もあります。
さらに、モビリティー事業は従来の交通手段や既存のビジネスモデルと競合する場合もあります。
例えば、従来のタクシーサービスや公共交通機関との関係性や競争が発生するかもしれません。
しかし、モビリティー事業は、持続可能な交通システムの構築や都市のモビリティーの改善に向けた可能性を秘めています。
技術の進歩や新たなビジネスモデルの導入により、効率的な交通システムや低炭素な移動手段の普及が進むことが期待されているのです。
関連記事:なぜトヨタは「モビリティ・カンパニー」へモデルチェンジしたのか
まとめ
モビリティー事業は交通や移動に関連するサービスや技術の提供を通じて、より便利で持続可能な移動手段を実現するための取り組みを指します。
これにより、人々の移動の利便性や効率性が向上し、都市の交通問題の解決や持続可能な社会の構築に寄与することが期待されています。
あらゆるものが変革していく時代に、車もモビリティへの変革をしているのです。
関連記事:2人乗りの超小型EV(電気自動車)とは?超小型モビリティについて解説