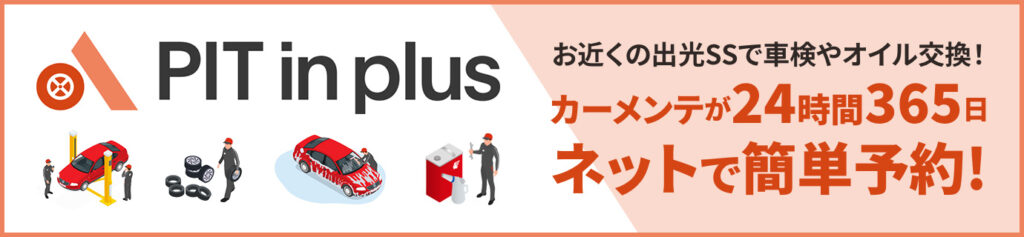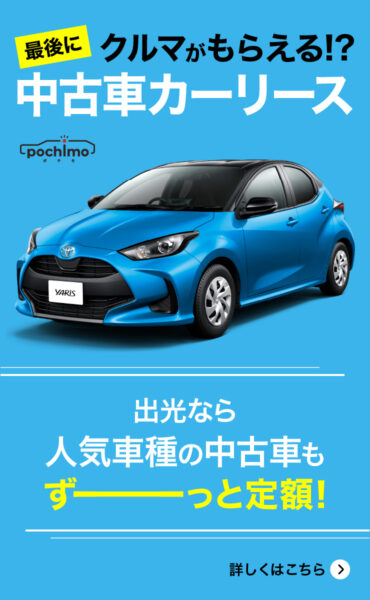ユーザー車検のやり方・流れを紹介!業者を介した場合と比較!

車を所有している人の多くは「車検は業者に任せるもの」と考えているでしょう。
車検には、業者に依頼するやり方のほかに「ユーザー車検」があります。
ユーザー車検については詳しく知らないという人も多いかもしれません。
この記事では、2つの車検のやり方や流れを解説しますので、ぜひ理解してチャレンジしてみてください。
ユーザー車検をやってみることで、費用を抑えたり、知識が深まったりします。
関連記事:車検に必要な時間はどれくらい?時間を短縮するポイントを紹介
INDEX
車検のやり方は2種類ある

車検のやり方は2種類あります。
一つは車検の全工程を業者に依頼する方法で、もう一つは「ユーザー車検」と呼ばれるやり方です。
ユーザー車検は予約から受検まで全ての手続きを車の所有者自身が行います。
車検を業者に依頼する場合は、まずガソリンスタンドやカー用品店、ディーラーや車検専門店などから見積もりをもらい、検査内容や費用に納得できた業者へ必要書類を提出すれば、車検の手続きや作業の全てに対応してくれます。
またユーザー車検にも、車を検査場に持ち込み検査を受ける工程のみを業者に依頼できる「車検代行」というサービスもあります。
車検代行では、車検の予約、検査の手続きや立ち合い、必要最低限の整備などを依頼できます。
関連記事:PIT in plusで車検の期間や日数を管理!定期的なメンテナンスも!
ユーザー車検の流れとやり方

業者に依頼すると自分で手続きをする手間がなく便利ですが、実際の車検にかかる費用以外に手数料が発生します。
一方、ユーザー車検は自分で手続きを行うため、手数料分のコストを抑えられます。
ユーザー車検はどのように進めればよいのでしょう?ここではそのやり方を解説します。
【STEP1】車検を予約する
まず車検証かフロントガラス上部に貼られているシールで車検の有効期限を確認し、期限の1ヵ月以内の日取りで車検の予約を取りましょう。
車検を受ける会場は、普通車は運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会となります。
車種によって異なるため注意しましょう。
予約はインターネットから可能です。
普通車であれば「自動車検査インターネット予約システム」、軽自動車の場合は「軽自動車検査予約システム」へアクセスしてください。
【STEP2】準備(必要書類・費用・事前点検・整備)
車検の予約が完了したら、必要となる書類や費用を準備します。
車検を受けるにあたって必要な書類は以下の通りです。
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
- 自動車税(種別割)納税証明書または軽自動車(種別割)納税証明書
- 印鑑(認印可)
また、車検に必要な費用は自賠責保険料と自動車重量税、検査手数料の3種類です。
自賠責保険料は車種によって若干の変動がありますが、軽自動車・普通自動車の場合は21,000円程度です。
自動車重量税は、所有している車の重量やエコカー減税の対象車かどうかで税額に違いがあります。
また、高い費用を出して車検に出したものの、不備や不具合が見つかり車検に通らないケースもあり得ます。
こうした事態を防ぐためには、自身で事前点検を行い不具合を解決しておく必要があります。
不安がある場合は、民間が運営している予備検査場を利用するのも一つの方法です。
法定点検項目も見ないといけないので、合わせて考えておきましょう。
関連記事:法定点検を受けないデメリットは?車検と比べて重要度は低い?
【STEP3】車検場で手続きを行い、検査を受ける
車検当日は、車検場にていくつかの手続きを行います。
費用を先払いする場合は手続きの前に自動車重量税と検査手数料を支払います。
支払いの際は、窓口で自動車重量税と検査手数料分の印紙・証紙を購入し、必要書類に貼り付けます。
検査当日は、以下3種の書類の記入が必要です。用紙は検査場に置いてあります。見本を見ながら記入しましょう。
- 自動車検査票
- 自動車重量税納付書
- 継続検査申請書
支払いと手続きが済んだら、コースに出て検査を行います。
検査項目ごとの指示に従い、車を運転・操作します。
なお検査コースには1日3回までしか入れません。
3回とも不合格となった場合は、後日再検査を受ける必要があります。
関連記事:車検はどこが安い?業者別の相場や特徴、安く抑える方法を解説!
【STEP4】合格すれば車検証が交付される
車検に合格すると、新しい車検証と検査標章(車内に貼るシール)が交付されます。
もし当日中に合格できなかった場合は、検査場で「限定自動車検査証」を発行してもらいます。
不合格の場合は、原因となった箇所を整備した上で2週間以内に再検査を受ける必要があります。
限定自動車検査証があれば、修理中に車検の満了日を過ぎてしまっても公道を走れます。
検査日から2週間以内であれば、不合格の原因となった箇所のみ再検査すれば問題ありません。
2週間を超えてしまった場合は、全項目での再検査が必要になります。
関連記事:2023年7月3日車検シールの位置変更にあたっての対応方法
車検を業者に依頼する場合の流れとやり方

ユーザー車検は自身でさまざまな手続きをしなければなりませんが、車検業者に依頼する場合はさほど手間のかかる手続きはありません。
ここでは、業者を利用した車検のやり方・流れを解説します。
【STEP1】車検業者を決めて予約する
まず複数の業者から相見積もりを取り、検査内容や料金を比較しましょう。
その上で依頼する車検業者を決めるのがおすすめです。
業者や時期によってはキャンペーンや割引を実施している場合があります。
少しでもお得に利用したい人は、見積もり依頼時に特典を確認しておくとよいでしょう。
業者が決まったら予約を入れます。
この際、車検満了日の2ヵ月ほど前に予約すると希望の日時を取りやすいでしょう。
車検期間中に代車が必要な場合は予約のタイミングで依頼するのが一般的です。
車検費用を現金以外の方法で支払いたい人も、予約時に確認しておきましょう。
関連記事:車検を早く受けると損?車検を受けるタイミングも併せて解説
【STEP2】必要書類・費用などを準備する
予約が完了したら、車検に必要な書類・費用を準備しましょう。
業者を通して車検を受ける際は、以下の書類が必要になります。
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
- 自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)
- ※軽自動車の場合は軽自動車税(種別割)納税証明書
- 車検費用(自賠責保険料、自動車重量税、検査手数料)
- 印鑑
車検にかかる費用は業者によって差があります。
車検当日になって、整備・交換が必要な部品が新たに見つかることもあるでしょう。
当日は、見積もり額より少し多めの現金を用意しておくと安心です。
また検査場に車を持ち込む前に、念のため車内から貴重品は持ち出しておきましょう。
関連記事:軽自動車の納税証明書がなくなったらどうすればよい?再発行の手続きの流れと必要書類を紹介
【STEP3】車検業者に車を預けて、完了次第受け取る
予約当日は検査場まで車で向かい、業者に車を預けるのが一般的です。
代車を申し込んでいる場合は、このときに代車に乗り換えます。
提示された車検終了予定日時にあらためて検査場へ出向き、車と新しい車検証、検査商標のシール、自賠責保険証明書などを受け取ります。
業者によっては、現在の車の状態や車検時に見つかった気になる点、今後のメンテナンスなどについてアドバイスしてくれます。
整備にかかった費用や部品交換があった場合など、車検費用と別に発生した料金はこの引き取りのタイミングで支払う場合が多いです。
関連記事:車検にかかる日数はどれくらい?車検での検査項目や流れも紹介
車検を受けなければならない理由
日本で車を所有するにあたって、車検は必ず受けなければなりません。
このことは「道路運送車両法」という法律によって義務付けられています。
車検が切れた車に乗って公道を走行すると法律違反となり、6ヵ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。
車検には、定期的に適切な車の整備を行うことで不具合によるトラブルや事故を最小限に抑えるという役目があります。
愛車を長く安全に乗るためにも、車検の受け忘れには気を付けましょう。
関連記事:予備検査と車検は何が違う?予備検査を実施するメリットや注意点を紹介
まとめ
車検には「業者に依頼するやり方」「自分で車検を通すやり方(ユーザー車検)」の2つがあります。
ユーザー車検を実施するには、車に関する一定の知識が必要ですが、一度やってみると知識が深まります。
業者に依頼する場合は、見積もり依頼や予約など早めの行動が大切です。
車検は車の所有者に課せられる義務であるため、満了日までに必ず受けましょう。