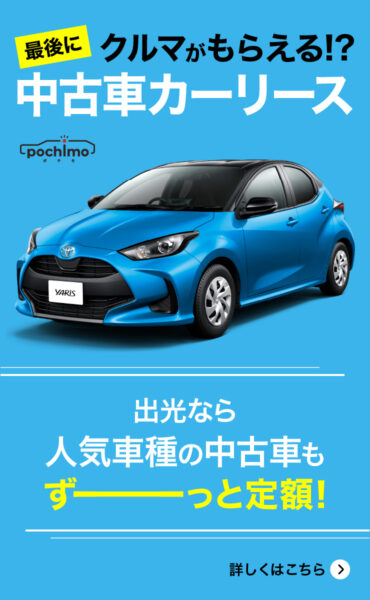EV車とハイブリッド車の違いとは?それぞれのメリット・デメリットを解説!

2021年1月18日に始まった通常国会において、国内販売車の電動化について「2035年までに新車販売で電動車100%を実現する」と表明されたことにより、以降で国内の自動車業界は電動車の開発へ注力する動きを強めました。
現代の自動車市場では、環境に優しい選択肢としてEV車(電気自動車)と、かねてから人気のあるハイブリッド車が注目されています。
この記事では、EV車とハイブリッド車の違いを解説し、それぞれのメリットとデメリットを詳細にご紹介します。
それぞれの違いを理解することで、車選びの参考になれば幸いです。
関連記事:【2024年】国産BEV(電気自動車)一覧!メリット・デメリット・ランキングも紹介!

INDEX
EV車とハイブリッド車の違い
EV車は、環境への影響が非常に小さく、運用コストが低い点が魅力ですが、充電インフラの整備が追いついていない地域では不便を感じることもあります。
ハイブリッド車は、燃費の良さと環境負荷の軽減を両立しつつ、航続距離や充電の心配が少ないため、現在のインフラでも利用しやすい選択肢と言えます。
EV車とハイブリッド車は、それぞれ違うメリットとデメリットを持ち、ユーザーのライフスタイルや使用目的によって最適な選択肢が異なります。
詳しくメリットとデメリットを見ていきましょう。
関連記事:ガソリン車はいつまで乗れる?日本の取り組みや他車のメリット・デメリットを紹介
EV車(電気自動車)の特徴

EVとは「Electric Vehicle」の略称で電気を動力として走る車全般のことを指します。
EVを電気自動車と呼ぶこともありますが、電気自動車はBEV(Battery Electric Vehicle)と表すのが正しい表現であり、バッテリーの電気のみを動力として動く車のことを指します。
また、EVの電力を補給する方法にもさまざまな種類があり、充電スタンドを用いて電力を補給するものもあれば、自動車そのものの機能で発電するものも存在します。
関連記事:これから車を買うなら電気自動車(EV)?今後の展開も予想
EV車のメリット
現在広く普及しているガソリン車に対して、EVのメリットにはどんなものがあるのでしょうか。
ここでは、EVの持つメリットについて紹介していきます。
維持費が抑えられる
現在燃料として利用されるガソリンの価格よりも電気の価格の方が安価であることから、EVは維持費を抑えることができます。
特にBEVについては電気のみを使用するため、費用面でのメリットは大きくなります。
また、深夜に電気代が割引されるプランを契約し、車を夜間に充電することでも維持費を抑えることが可能です。
ただし、この場合には自宅に専用のスタンドを設置するコストがかかるため、設置費用と場所の確保が発生します。
関連記事:車の維持費を抑えるコツとは?「維持費って馬鹿らしい!」と感じる方へ
非常用の電源として使用できる
EVは災害などで停電した際や屋外で電源がない場合に、バッテリーに溜めた電力を他の電子機器に供給する電力源として活用することができます。
充電を満タンにした場合、1人が生活するための電力を1週間前後ほど補えると言われています。
また、1度に出力できる電力も1500Wとなっており、ドライヤーなど電力消費が大きな電化製品も問題なく使えます。
関連記事:EVを家庭用電源に活用するV2Hが普及!仕組みやメリットとは?
走行が静かで乗り心地が快適
EVは電気モーターを利用して走行するため、ガソリンエンジンを使用する車と比較して振動と騒音が抑えられます。
車内に揺れや音が伝わらないため、同席者にとっても快適な乗り心地を体感できます。
また、モーターはアクセルを踏んだ側から最大トルクを発揮できるので、快適さに加えてパワフルさを兼ね備えています。
環境への影響が小さい
CO2排出量がゼロであり、大気汚染の原因となる排気ガスを出さないこともメリットとして挙げられます。
環境への意識は少し前まで大事だけど自分には関係ないという対岸の火事的なものが多かったのですが、近年は真剣に自分のことのように環境問題を高く意識する方が多くなっているため環境への影響も堂々とメリットと言えるようになりました。
関連記事:電気自動車(EV)の仕組みって?種類や充電方法、SDGsへの貢献を解説
EV車のデメリット

EVには環境面や機能面でのメリットがある一方で、普及に向けた問題点やデメリットも存在します。
ここでは、EVのデメリットについて紹介していきます。
関連記事:いくら夢や理想を語っても、充電スタンドをつくっても電気自動車は普及しない
充電が完了するまでの時間が長い
EVは電気で走行するため、専用の充電スタンドで充電する必要がありますが、充電完了までに時間を要する点で不便さがあります。
家庭用の充電スタンドの場合、充電を満タンにするためには7時間ほど充電しなければなりません。
ショッピングモールや道の駅などに置いてある急速充電スタンドを利用することで充電のスピードを早めることもできますが、それでも充電には30分以上かかります。
買い物や食事をしている時間を充電に充てるなど、上手に時間を使いながら充電完了を待つ必要があります。
ガソリン車の場合であれば、ガソリンを満タンまで入れたとしても数分であることを考えると、充電完了までの時間が長い点は普及にあたっての今後の課題となります。
関連記事:第10回を迎えた白馬EVラリーに三菱ekクロスEVで参加
充電場所を探すのに手間と時間がかかる
EVは国内でも都市部を中心として浸透が進んできてはいますが、それでも充電スタンドを目にする機会はまだ少ないのが現状です。
そのため、EVを利用する際は道中に充電スタンドがあるかどうかを事前に確かめておく必要があります。
現状、充電スタンドはショッピングモールや道の駅がある箇所に集中しており、地方など需要が低い地域ではまだ十分に配置されていません。
そのため、EVの購入を検討する際は、必ず周辺地域に充電スタンドがあるかどうかを確認しておきましょう。
関連記事:EVの航続距離はどれくらいなのか?ガソリン車との違いも解説
車体価格が高い
EVの直近の課題として、車体価格が高いという点が挙げられます。
エントリーモデルであっても300万円以上が必要となり、ガソリン車であれば100万円台で購入できる点を考えると、やはり車体価格の点で見劣りしてしまいます。
EVの購入にあたっては税金面の優遇や各種補助金の制度を受けられるものの、それでもなお200万円を超えます。
人生の中でも大きな買い物となりますので、購入にあたっては購入後の維持費も含めて慎重に検討しましょう。
関連記事:サポカーやCEVの補助金はもう申請できないの?自動車補助金についても紹介
ハイブリッド車の特徴

ハイブリッド車は、ガソリンエンジンと電気モーターを併用して駆動する自動車です。この二つの動力源を効率的に使い分けることで、燃費を向上させ、CO2排出量を削減します。
関連記事:これから車を買うならハイブリッドカー!おすすめ車種10選を紹介!
ハイブリッド車のメリット
ハイブリッドのメリットとしては以下のようなものが挙げられます。
燃費の良さ
エンジンと電気モーターの併用により、従来のガソリン車に比べて燃費が良いです。
例えばトヨタのヤリスのWLTCモードカタログ燃費では、ガソリン車21.3km/L、ハイブリッド車36.0km/Lと驚異的な数値を記録しています。
関連記事:WLTCモードとはどのような基準?実燃費との差異について解説
運転のしやすさ
エンジンとモーターの自動切り替えにより、スムーズな加速と走行が可能です。
いきなり電気自動車に乗ると戸惑うかもしれませんが、ハイブリッドではほぼ違和感がないでしょう。
ハイブリッド車のデメリット
一方でハイブリッド車にもデメリットは存在します。
ガソリン車よりは車両価格が高い
EV車と比べると初期コストは低いが、従来のガソリン車に比べるとやや高価です。
先述のヤリスはガソリン車は税込1,501,000円〜、ハイブリッド車は税込2,044,000円〜と価格に差が出ています。
メンテナンスが複雑
エンジンと電気モーターの両方を持つため、メンテナンスが複雑になる傾向があります。
さらに各会社で呼び方が違うものが多く、トヨタのE-Fourや、日産e-POWER、ホンダe:HEVと名前がそれぞれ違う上に、仕組みも微妙に違うため、メンテナンスや取り扱いの難しさに拍車をかけています。
関連記事:EV ソルテラは補助金でいつまでお得に?減税制度を解説!
他の動力源の種類とそれぞれの特徴について

EVには電気自動車(BEV)以外にもプラグインハイブリッド車(PHEV)や燃料電池自動車(FCV)という種類のものもあります。
ここでは、それぞれについて特徴を紹介していきます。
ガソリンと電気を使ってバランスよく走るPHEV
PHEVは「Plug-in Hybrid Electric Vehicle」の略称でプラグインハイブリッド車のことを指します。
BEVが電気のみを走行のエネルギーとしているのに対して、PHEVはガソリンと電気の両方を走行のエネルギーとしています。
電気の供給はBEVと同様に専用の充電スタンドで行います。
関連記事:PHV車とは?メリットやデメリット、PHV車がおすすめの人についてご紹介
関連記事:PHV(PHEV)とはどんな車種?電気自動車(EV)との違いやおすすめの3台を紹介
水素の力で電力を生み出すFCV
FCVは「Fuel Cell Vehicle」の略で燃料電池自動車のことを指します。
水素の力で電力を生み出し、その電力でモーターを回転させて走行します。
水素を電力とする方法には2種類あり、水素を燃やして動力を得ているタイプと水素と酸素を反応させて電力を得ているタイプがあります。
このうち、一般的には後者のタイプのことをFCV(FCEV)と呼びます。
他の車種と大きく違う点は電池の種類です。BEVやPHEVはバッテリーを搭載しているのに対して、FCVは燃料電池を搭載しているため自力で発電することができます。
ただし、専用のステーションで水素を補給する必要があるという点では、まだ普及に向けて十分な環境整備が整っているとはいえないようです。
関連記事:燃料電池自動車(FCV)はどういった仕組みなのか?普及に向けた課題も紹介
まとめ
今回はEVについて種類や概要、メリットやデメリットを紹介してきました。
電気を動力として走行する自動車全般を指すEVは、今後広く普及されていくことが見込まれていますが、現時点においては充電や車体価格の面で課題が残ります。
環境に優しいエネルギーで車を利用でき、非常時の電源としての利用や維持費が比較的抑えられるというメリットもあるため、今後の技術の進歩や価格帯の変化についてアンテナを張って注視しておきましょう。